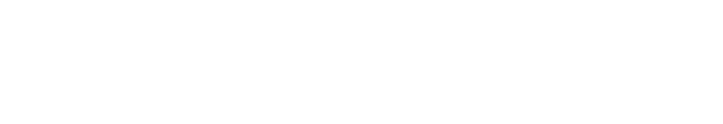よくある質問 (FAQ)
こちらでは、お客様からよくいただくご質問とその回答を掲載しております。お問い合わせいただく前に、ぜひご参照ください。
L型擁壁編
L型擁壁の載荷重 10(kN/m2)はどういうことですか
L型擁壁の設計に用いる自動車荷重として、載荷重の 10(kN/m²)が多く採用されていますが、これは25トン自動車の総重量を車両占有面積に分布させたものです。
・20トン自動車の場合は、20 ÷( 7×2.75)= 1.04(t/m²)→ 10.2(kN/m²)
・25トン自動車の場合は、25 ÷(11×2.50)= 0.91(t/m²)→ 8.9(kN/m²)
となることから、載荷重 10(kN/m²)となっています。
L型擁壁の地盤が悪い場合はどのような対策がありますか
施工場所の地盤支持力が、L型擁壁設計計算書に示される地盤支持力Q1の3倍以上あることが安定条件となります。従って、悪い地盤の場合は良質地盤まで置き換えや土質改良を行うか又は杭基礎を行うなどの対策が必要になります。
L型擁壁の根入れはどれくらいとればよいですか
L型擁壁の計算においては、根入れによる受働土圧は考慮していませんので、安定計算上では根入れが無くても問題ありません。しかし、根入れが無いため基礎が洗掘されたり人工的に損傷を加えられたりした場合は沈下等の原因になり、擁壁全体の安全性に影響を及ぼします。従って、一般的には500mm以上の埋め戻しを行い、どうしても無理な場合は厚さ50mm以上の張りコンクリート等で保護します。ここで、根入れは『底版の下面から500mm以上』と『底版の上面から500mm以上』の2種類の考え方があります。
L型擁壁の厚さと底版幅は関係ありますか
L型擁壁のたて壁や底版の厚さが厚くなると重量が増えますので、安定性が良くなるように思えます。従って、そのぶん底版幅が短くなりそうですが、実際はあまり大差がありません。具体的な計算例として、厚さを2倍で計算しても底版幅の差はわずか10mm〜20mmです。ゆえに、L型擁壁の厚さは底版幅に大きな影響は与えません。
L型擁壁の水抜きはどうしていますか
水抜きは、L型擁壁の裏面の水を排水するためのもので、宅地造成等規制法施行令や国土交通大臣認定擁壁を参考にして、壁面の面積3m²以内ごとに直径が55mm以上の穴を1個設けるようにしています。具体的には、高さが3000以下は直径が65mmの穴を水平方向に2個、高さが3000を越える場合は直径が75mmの穴を鉛直方向に2個設け排水できるようにしています。
L型擁壁のたて壁に模様を付けられますか
一般的には特殊樹脂化粧型枠(モールドスター)をたて壁の型枠内側に装着して凹凸模様の「割り石模様」「鉄平石張り石模様」「石乱積み模様」「洗い出し模様」「はつり模様」「レンガ積み模様」「タイル貼り模様」などの和風から洋風まで色々できます。その他、着色や絵模様もできますが、主な注意点は下記のとおりです。
- 化粧型枠の寸法の関係から、製品長が900又は1800が多くなります。
- 化粧型枠の厚さだけ余分に断面厚さや底版幅が必要になります。
L型擁壁のコーナー部や曲線部はどうしていますか
コーナー部や曲線部に標準製品を使うと、隣接する底版が当たるためたて壁の接合部に隙間が生じます。交角が大きい場合や曲線半径が小さい場合は、隙間が大きくなり目地モルタルだけでは対応できませんので、下記のような方法で対応します。なお、隣接する底版が開くように曲がる場合は何ら問題ありません。
- 高さが3000以下は、前面の製品長を2000mm、背面の底版端部の製品長を1900mmの平面形状が等脚台形になるようにしました。この形状により、高さ1000の場合15.5m、高さ2000の場合27.0m、高さ3000の場合38.0mの曲線半径までは標準製品を使用できます。
- 高さが3000を超える場合は、平面図に記された交角や曲線半径をもとにして、どれくらいの隙間が生じるかを計算し、隙間を解消するために切り取る部分の寸法を決めます。この方法は、高さ3000 以下で標準製品が使用できない場合にも用います。
L型擁壁天端の調整はどうしていますか
天端の調整コンクリートは場所打ち鉄筋コンクリートとし、その構造は下記のようにします。
- 調整コンクリートの高さは、標準の土質の場合、最大で500mmまでとします。
- L型擁壁は、調整コンクリート上面から底版下面までの高さを満足する製品の頭切りしたものを使用します。
- L型擁壁天端にはM12のインサートナットを250mm間隔で取り付けています。
- 調整コンクリートは、設計基準強度 24N/mm²で断面厚さは 100mmとします。
- 上下方向の主鉄筋は D13 の一端にねじ加工を施したものを用い、インサートナットにねじ込みます。延長方向の配力鉄筋は通常 D13 を1本配筋しますが、調整高さが高く間隔が300mmを越える場合は、さらに1本追加することがあります。
L型擁壁の強度試験はどのようにしますか
L型擁壁の強度試験専用の試験機がありますので、それにより試験を行います。試験方法は、L型擁壁を試験機に据え付け、底版と試験機を固定し、それから試験機の加圧部から水平方向に荷重を加えて、たて壁や底版に幅0.05mmを超えるひび割れの有無を調べます。ここで、荷重は設計計算書による『たて壁に作用する土圧力の水平分力』で、載荷位置は擁壁高さから底版厚さを除いた高さの1/3の位置になります。
L型擁壁は衝突荷重に対応していますか
現在のL型擁壁は、載荷重と土圧に対して設計されており、衝突荷重には対応していません。衝突荷重に対応させるためには、衝突荷重を受け止める1スパンの長さを仮定し、別途に底版幅・断面厚さ・鉄筋量を決定し、特別な製品を作る必要があります。
最近、擁壁類の天端部に設置し単独で衝突荷重に対応できる製品(プレキャストガードレール基礎)が開発されています。
プレガードとは何ですか
擁壁類の天端部に設置し単独で衝突荷重に対応できる製品(プレキャストガードレール基礎)のことです。平成11年3月に(社)日本道路協会「道路土工−擁壁工指針」が改訂され、『擁壁の頂部に車両用防護柵などを直接設ける場合、原則として安定計算およびたて壁の部材設計には防護壁に作用する衝突荷重を考慮するものとする』が明記されました。この文章を受けてL型擁壁を設計すると、従来の標準型に比べて莫大な大きさになります。また、既設の擁壁類も対応できないものが多くでてきます。プレガードは、新設の擁壁類にはもちろん、既に施工済みの擁壁類も天端部を少し工事すれば、たて壁や底版に作用する荷重を大きく低減することができ、全体を造り直したり大幅な補強をしたりする必要がありません。
通常のL型擁壁を逆L型擁壁として使用することができますか
逆L型擁壁は、たて壁において通常のL型擁壁と反対の面から土圧を受ける構造となるため、主鉄筋の位置が通常のL型擁壁と異なります。又、製品の鉄筋コンクリート重量・底版上部の土の重量・根入れによる受働土圧の1/2を抵抗力として考慮しているため、根入れ深さが重要になります。この場合、前面の根入れ部は雨水等による洗掘・人工的な掘削・凍結融解による緩みなどが発生しないことが必要条件です。以上のようなことから、通常のL型擁壁を逆L型擁壁として使用することはできません。
国土交通大臣認定L型擁壁で注意することは何ですか
このL型擁壁は、宅地造成等規制法施行令15条の規定に基づき、国土交通大臣の認定を受けた擁壁(以下、認定擁壁と呼ぶ)で、その権威と安全性を尊重するため下記の事項は十分注意して厳守して下さい。
- 認定擁壁は、安定計算において載荷重のとりかたが道路擁壁と異なり底版幅が短くなっているので、道路擁壁に使用できません。
- 載荷重は10kN/m²となっているので、大型の建物を建設する場合は、あらかじめ地表面に及ぼす荷重の大きさを確認し、10 kN/m²を越える場合は影響しない範囲まで建物を後退させるなどの対策をとって下さい。
- コーナー部の内角が90°以上180°未満は一体型の製品を使用することができますが、一体型の製品が無い場合や90°未満の場合は場所打ち擁壁になります。
- 当社では、90°から180°まで角度自在の型枠を持っていますので、90°から180°までは、いかなる角度にも対応できます。
- 埋め戻し土の沈下を見込んだ余盛りは300mmまでは認められていますが、これを当初の計画段階からの地盤高にしてはいけません。
- たて壁天端に差し筋を行い、空洞ブロックを設置することはできません。
- たて壁の接合部には5mmの隙間を設けており、ここから裏面の浸透水を排水するようにしているので、モルタル等をつめてはいけません。
側溝編
ニューパワー側溝は25トン自動車が通行しても大丈夫ですか
大丈夫です。ニューパワー側溝は、車両制限令第3条による25トン自動車の後輪一輪荷重を用いて、JPCS-RC 7253 落ちふた式U形側溝(JIS A 5372 附属書5路面排水溝類 推奨仕様 5-3 落ちふた式U形側溝に適合)に示される計算方法で設計しています。
ここで、路面載荷重は、後輪一輪荷重5トンをタイヤ接地幅0.5(m)で単位長さ当たりの等分布荷重に換算した10(tf/m²)【100kN/m²】を用いています。
ニューパワー側溝の特徴はどのようなところですか
ニューパワー側溝の大きな特徴は次のとおりです。
- 平成20年1月18日付で、新JIS認証制度のもと、JIS A 5372 プレキャスト鉄筋コンクリート製品 附属書5路面排水溝類 推奨仕様 5-3 落ちふた式U形側溝のII類認証を取得しています。
- 側溝の長さを2500mmにしたので、施工延長が大幅に延び、工期の短縮が出来ます。1日の施工目安は、50(基)【125m】を参考にして下さい。
- 両端は長さ500(mm)のU形部、中央部は長さ1500(mm)の暗渠部とし、モルタルによる目地作業が簡単に出来ます。
- 曲線施工の場合や調整用は、長さ500(mm)で対応します。
- 側壁外面を垂直としたので、埋め戻しや転圧が簡単に出来ます。また、ブロック塀や擁壁がある場所でも近接施工が出来ます。
- 蓋と側溝の接触部は凹型円弧の線接触となりますので、消音効果が期待出来ます。
- ずれ止めピンを使用しますので、施工時のずれが無く、効率よく施工出来ます。
- 側溝上面にメッシュ模様の溝と断面の中央部にスリットを設けたので、道路の表面水を速やかに排水出来ます。
ニューパワー側溝はどのような場所に使えばよいですか
普通の側溝と同じ場所に使える事はもちろんですが、次の場所には最高の機能を発揮します。
- 直線部の道路は、施工性が良く、施工後の状態が壮観で美しいです。
- 緩やかなカーブの道路も、施工性が良く、施工後に美しい曲線を描き、周囲の景観に馴染みます。
- 小さいカーブの道路は、長さ500(mm)の側溝を使う事で、滑らかな曲線となり、満足のゆく道路が出来上がります。
- 道路の表面排水を速やかに行いたい場所。
- 市街地や埋立地などで、水路勾配が取れない場所。
- 同じ区間の中で、コンクリート蓋の部分、グレーチングの部分、暗渠の部分、上部に横断勾配がある部分などが不規則に設けられる場所。
セントレーン側溝とは何ですか
セントレーン側溝は、管渠型側溝で、基本的な考えはJPCS-RC 7253落ちふた式U形側溝(JIS A 5372 附属書5路面排水溝類 推奨仕様 5-3 落ちふた式U形側溝に適合)に準じています。両面勾配型と片面勾配型の違いは次に示すとおりです。
片面勾配型〜全断面が暗渠型で、管渠型側溝として使用します。上面は車道側から歩道側に向かって6(%)の勾配で傾斜を設けています。使用場所は、車道と歩道の境界で、歩道側の上面には歩車道境界ブロックを設置します。
両面勾配型〜全断面を暗渠型とし、上面は左右から断面中央に向かって2(%)の勾配で傾斜を設けています。使用場所は、車道と歩道の境界で、バリヤフリー等の関係で段差を設けたくない部分に設置します。
鉄筋コンクリートベンチフリュームとは何ですか
通常の側溝は、道路・宅地・山林などの水を速やかに排水することを目的に使用するため、雨天の日以外は内部が空になっています。ところが、水田では貴重な農業用水を隅々の田までまんべんなく送り、3ヶ月位は絶えず水が流れている必要があります。
そこで、送水に対する様々な実験を重ね、下記のような特徴を備えた農業用側溝が完成しました。
- 基本的な考えは、農林水産省構造改善局「土地改良事業標準設計第5編.鉄筋コンクリート二次製品水路解説書」(現在は、農林水産省農村振興局 土地改良事業標準設計図面集 鉄筋コンクリート二次製品)に準拠しています。
- 一般自動車の影響を考慮した載荷重 15 kN/m²で断面厚さと鉄筋量を決めていますが、大型自動車が直近を頻繁に走行する場所には使えません。
- 安価で施工性が良く、漏水の少ない継ぎ手にしています。
- 水田と水田の間に施工することが多いため、出来るだけ質量を軽くしています。特に、枝線で使用する300以下は人力で移動ができます。
急勾配に施工しますが、問題がありますか
農林水産省の仕様書では、流速が3.0(m/s)を超える場合は内面に厚さ15mmのコンクリートを打設して、水流による摩耗などに耐えるような措置をとる事が決められています。
工場製品の側溝に厚さ15mmのコンクリートを打設する事は困難な場合も考えられますので、下記の様な対応が考えられます。
- (1)新旧打ち継ぎ用の接着剤を工場製品の側溝に塗り、その後厚さ15mmの無収縮モルタルを塗ります。/li>
- (2)厚さ15mmのコンクリートの代わりに繊維混入樹脂等でライニングする事も出来ます。コンクリートよりも耐久性に優れます。/li>
- (3)あらかじめ、厚さ15mmだけ無いものとして、設計計算を行ってみます。これで問題が無ければ側溝は安全と言えます。
上記の(1)及び(2)は、技術的には問題ありませんが、接着剤や樹脂等の材料費が割高となり経済性に問題が生じます。
余談ですが、約23年前に17%〜21%の急勾配(水深4cm位で流速が3【m/s】を超える)に施工された鉄筋コンクリートベンチフリュームを調べたところ、底部に少し摩耗がある(粗骨材が露出)程度で、その他は何ら問題がありませんでした。
U字溝はどのようなところに使用しますか
排水側溝の原点とも言え、コンクリート製品の中で歴史が有り、金額が安く施工が簡単なことから広く普及しています。主な使用場所は、下記のとおりです。
- 農道や林道の雨水排水側溝
- 住宅街の雑排水側溝
- 公園や広場周辺の雨水排水側溝
- 工場や大規模施設周辺の排水側溝
U字溝は一般道路に使用できますか
U字溝はJIS A 5372(プレキャスト鉄筋コンクリート製品)付属書5 路面排水溝類 推奨仕様5-1 U形側溝、推奨仕様 5-2 上ぶた式U形側溝に分けられ、U形側溝は「主として車道に平行して設置するもの」、上ぶた式U形側溝は「1種が主として歩道に設置するもの、2種が車両(後輪一輪32kN以下)が隣接して走行することはまれで、走行することがあっても一時退避などで低速で走行するような場所に、車道に平行して設置するもの」と規定されています。
ボックスカルバート編
ボックスカルバートとは何ですか
ボックスカルバートは日本語に直しますと、ボックス (箱形) カルバート (暗渠) となり箱形暗渠と表されます。
主として、雨水排水の管路として場所打ちされていたものが、工場で製造されるようになりました。
施工及び工事費等で場所打ちやヒューム管の巻き立てよりも優位性が有り、近年その普及は著しいものがあります。
主な特徴を下記に示します。
- 種類…平成16年3月20日付で、JIS A 5373 プレキャストブレストレストコンクリート製品 附属書4 暗きょ類 推奨仕様 4-2 ブレストレストコンクリートボックスカルバートに規定されるPCボックスカルバート、JIS A 5372 プレキャスト鉄筋コンクリート製品 附属書3 暗きょ類 推奨仕様 3-4 鉄筋コンクリートボックスカルバートに規定されるRCボックスカルバート、(社)日本下水道協会?類認定のPCボックスカルバートとRCボックスカルバートの4種類に分かれます。
当社は、新JIS認証制度のもとで、JIS A 5372 プレキャスト鉄筋コンクリート製品 附属書3 暗きょ類 推奨仕様 3-4 鉄筋コンクリートボックスカルバートに規定されるRCボックスカルバートのⅡ類認証を取得しています。その内容は、500×500から5000×5000まで136種類で、設計条件は自動車荷重245KN、土被り0.2m〜3.0mとなっています。 - 形状…内幅に対して内高さの比が0.5〜2.0位までの横扁平や縦扁平の製品、メガネ式の2連ボックス、下幅よりも上幅の広い逆台形ボックスなども製造されています。
- 施工方法…工事場所の状況に応じて、開削工法 ・オープン推進工法 ・沈埋工法・スライド式送り込み工法 ・台車移動工法 ・推進工法などを用いて施工します
縦締め工法とは何ですか
従来、コンクリート製品はモルタルを使用して接合していましたが、モルタルは硬化後に乾燥収縮等によりひび割れや肌離れが生じ、下水道事業などでは漏水の原因になり問題がありました。
そこで、接合面にゴムパッキン等を張り付け、PC鋼棒を用いて引っ張り力を加え、強制的に製品と製品を接合させる方法が考案されました。
漏水対策だけでなく、昭和53年の宮城県沖地震・昭和58年の日本海中部沖地震・平成7年の阪神淡路大震災においても異常のないことが確認されています。
施工場所が古い水路のため複雑な線形になりますが施工できますか
どんなに複雑な線形でも、直線部・屈曲部・曲線部に分けることができますので、工場製品のボックスカルバートを施工できます。
その方法を下記に示します。
- 線形を直線部・屈曲部・曲線部に分け、各区間の距離や交角や曲線半径を求めます。
- 直線部は、標準長さの製品と長さ調整用の直切り製品を組み合わせて配置します。
- 屈曲部は、交角をもとにして屈曲位置を対称とした片直台形の斜切り製品を用いる場合もあります。
この場合、直角側の断面が前後の直線部と連なるのは言うまでもありません。 - 曲線部は、交角と曲線半径をもとにして、偶数個の片直台形を組み合わせて曲線上に配置します。強度に影響のない範囲で、偶数の数を大きくしたほうが滑らかな曲線が形成されます。
ここでも、曲線区間の両端は斜切り製品の直角側の断面が前後の直線部と連なるのは言うまでもありません。 - 直線部の連結はPC鋼棒、屈曲部や曲線部の連結はPCより線を使用します
最近、道路と平行に設置される場合の設計方法が問題になっていますが…
ボックスカルバートが道路と平行に設置される場合は、日本道路協会「道路土工−カルバート工指針」に従えば、活荷重の計算方法は「共同溝指針」に準じるとなっています。 その「共同溝指針」の内容を下記に示します。
- 土被りが比較的ある場合
ボックスカルバートの断面方向は、衝撃係数や断面力低減係数を考慮した後輪二輪の荷重を車両占有幅2.75mで割ったものを頂版の全幅に載荷させます。ボックスカルバートの長さ方向(車両の進行方向)には接地長さ0.2mで45度の角度で分布させます。
これは、車両がボックスカルバートの上を横断する場合の荷重分布を90度回転させたものです。
土被りが2.9m以上の場合は、前輪二輪の荷重も加えます。 - 土被りが極端に浅い場合
後輪を集中荷重と見なして、接地幅0.5m、接地長さ0.2mの長方形分布荷重が各方向に45度の角度で分布するものとします。ここで、集中荷重を受ける頂版は両端固定の一方向スラブになりますので、コンクリート標準示方書(構造性能照査編)を参考にすれば、自由端方向に少し分布長さを加える事が出来ます。
従って、接地長さは45度で分布させた長さよりも長くなり、部分分布荷重もわずかながら緩和されます。
ここで、土被りが極端に浅い場合とは、どれくらいを指すのか疑問になりますが、過去の公的仕様書等から0.2m未満と判断して良いと思われます。
集中荷重の考え方は多数ありますが、上記の(1)から(2)に移る時、荷重の大きさ・曲げモーメントせん断力等が(1)よりも小さくなったり、極端に大きくなったりしないような考え方が重要です。
ボックスカルバートの大きさが変わる位置はどうしますか
路線によっては、幅の変化 ・ 高さの変化 ・ 幅と高さの両方が変化する位置が多数あります。
このような位置を場所打ちコンクリートで製造していては、工場製品の価値が半減します。そこで、板状で外幅と外高さは大きいボックスカルバートに合わせ、その内部に小さいボックスカルバートの内空断面に合わせた開口部を設けた板 (通称、断面変更板) を制作し、大きいボックスカルバートと小さいボックスカルバートの間に挟み、両者のボックスカルバートと締め付けを行います。この方法により、すべてが工場製品で施工でき、漏水対策や工期の大幅な短縮ができます。なお、ヒューム管とボックスカルバートの接続のように異種製品の接続もできます。
さらに、同じ断面で落差が生じる場所は、落差変更板を使用すると、マンホール等を設けるよりも工期が大幅に短縮され、大変簡単な工事となります。
マンホールや集水の穴はどのようにしますか
ボックスカルバートの施工延長が長くなると点検や掃除のためのマンホール、集水や採光などのための開口部が必要になります。
過去の実施例を次に示します。
- 浅い場所にマンホールを設ける場合
ボックスカルバートの上スラブにφ600の穴を開けておき、その上に調整部を設け、受け枠と鉄蓋を設置します。
極端に浅い場合、上スラブにインサートナットを3本埋め込み、受け枠と長ボルトで固定することもできます。 - 深い場所にマンホールを設ける場合
ボックスカルバートの上スラブにφ900の穴を開けておき、その上に場所打ちマンホールやコネクトホールを設けます。
コネクトホールの場合、上スラブとの接触周辺は厚さ150mmの防護コンクリートを打設します。 - 集水用の穴を設ける場合
ボックスカルバートの上スラブに300×300〜600×600の穴を開けておき、その上に場所打ちコンクリート壁を立ち上げ、上面にグレーチング用受け枠を埋め込み、グレーチングを取付けます。
極端に浅い場合は、上スラブにインサートナットを数本埋め込み、グレーチング用受け枠をボルトで固定し、周囲を無収縮早強モルタルで保護することもできます。
取付け管用の穴はどのようにしますか
ボックスカルバートにL型側溝等からの管を取付けるため、側壁に開口部を設ける場合があります。製品の呼び名と開口部の大きさは別途定めていますが、上下のハンチを避けた位置に設け、管の取付け後は隙間を無収縮モルタルで入念に仕上げます。
ボックスカルバートの耐震検討はどのようにしますか
ボックスカルバートの耐震検討は、平成13年4月に発刊された(社)日本下水道協会「下水道施設耐震計算例」に基づいて行います。断面方向及び長さ方向とも応答変位法で計算を行い、レベル2に対して安全であるかどうかを確認します。
製品と製品の接合部にはANB可とうジョイントを用いることにより、せん断変位・扇状及び伸縮変位・止水性能に異常がないようにします
ヒューム管編
ヒューム管とは何ですか
コンクリートの締め固めに遠心力を応用して成形された鉄筋コンクリート管で、1910年にオーストラリアのヒューム氏によって発明されました。わが国において製造販売されたのは1925年です。
遠心力の利点は何ですか
コンクリートの締め固め時の遠心力は、重力の25倍から40倍で、コンクリート中の水分がしぼり出され、水セメント比は30%以下の緻密で堅固なコンクリートになり、同一配合の振動締め固めコンクリートよりも約30%強度が増加します。
外圧管・内圧管・推進管の違いは何ですか
- 外圧管とは、地面に溝を掘り管を埋設して土を埋め戻したり(溝型埋設)、又は地面の上に管を設置しその上に土を盛り上げたりして(突出型埋設)、管の外面からの力(荷重〜外圧と呼びます)に対して耐えるように設計されている管です。
- 内圧管とは、農業用水などの送水に用いるパイプラインに代表されるように、ある一定期間は管の内部が満水状態にあり、かつ数m以上の水頭差(水による内部からの圧力で内圧といいます)が生じるような場所に使用する管で、主に満水による内圧と埋め戻し土による外圧に対して耐えるように設計されている管です。
- 推進管とは、地面に管や機械を降ろす穴(発進立坑)と次の発進立坑を兼ねた穴(到達立坑)を設け、発進立坑から様々な工法で地中に管を押し込み、到達立坑に向かって管を連続して押し込んでいくのに用いる管である。推進工法に適するように外圧管や内圧管に比べて管厚が厚くなっており、管端部には鋼製の接続具が装着されている。わが国でヒューム管による最初の推進工事は、昭和23年10月に大阪市でφ600が7mである。
1種と2種の違いは何ですか
管の外圧強さによって1種と2種に区別されており、厚さは変えずコンクリート強度と鉄筋量が異なります。2種のほうが外圧強さが大きいため、1種よりも過酷な埋設条件に対応できます。 2種の形状及び寸法は1種と同じですが、外圧強さの倍率は、外圧管で約1.4〜1.6倍、推進管φ700以下で約1.5倍、推進管φ800以上で約2倍高くなっています。
1種と2種の使い分けはどのようにしますか
- 埋設方法が溝型(地面に溝を掘る)か突出型(地面の上に設置)かを確認します。 溝型でも広い溝の場合や他の条件によっては、突出型となる場合があります。
- 埋め戻し土の種類が砂質か粘性かを確認します。
- 下水道工事では矢板の影響を考慮するかどうかも確認します。
- 自動車荷重の大きさと管の土被りを確認します。
- (社)日本道路協会「道路土工−カルバート工指針」の参考資料又は全国ヒューム管協会「ヒューム管設計施工要覧」に示される基礎形状選定図から1種と2種並びに基礎形状を選びます。
- 地域によって若干の差はありますが、1種の90度固定、1種の180度固定、2種の90度固定、2種の180度固定の順に強度と材工単価が高くなります。
マンホール編
マンホールとは何ですか
管渠の検査・維持点検・排気などの目的で、管渠の起点・屈折位置・勾配変化点・合流位置・直線部の中間位置などに設置します。汚水桝との違いは、管渠が本管で、内部に人間が入って維持点検ができる空間があることです。構造は、鉄蓋と受け枠・調整部・斜壁・スラブ・直壁・底部などからなり、総称してマンホールと呼びます。 呼び名と大きさは、次のとおりです。
- 0号マンホール
内径750mmの円形で、組立マンホールにおいて小規模な排水又は起点に使用します。 - 1号マンホール
内径900mmの円形で、管の起点及び600mm以下の管の中間点並びに内径450mmまでの管の会合点に使用します。 - 2号マンホール
内径1200mmの円形で、内径900mm以下の管の中間点並びに内径600mm以下の管の会合点に使用します。 - 3号マンホール
内径1500mmの円形で、内径1200mm以下の管の中間点並びに内径800mm以下の管の会合点に使用します。 - 4号マンホール
内径1800mmの円形で、内径1500mm以下の管の中間点並びに内径900mm以下の管の会合点に使用します。 - 5号マンホール
内のり2100mm×1200mmの角形で、内径1800mm以下の管の中間点に使用します。 - 6号マンホール
内のり2600mm×1200mmの角形で、内径2200mm以下の管の中間点に使用します。 - 7号マンホール
内のり3000mm×1200mmの角形で、内径2400mm以下の管の中間点に使用します。 - 特1号マンホール
内のり600mm×900mmの角形で、土被りが特に少ない場合や1号マンホールが設置できない場合に使用します。 - 特2号マンホール
内のり1200mm×1200mmの角形で、内径1000mm以下の管の中間点において、円形マンホールが設置できない場合に使用します。 - 特3号マンホール
内のり1400mm×1200mmの角形で、内径1200mm以下の管の中間点において、円形マンホールが設置できない場合に使用します。 - 特4号マンホール
内のり1800mm×1200mmの角形で、内径1500mm以下の管の中間点において、円形マンホールが設置できない場合に使用します。
組立マンホールとは何ですか
マンホール全体が工場製品で、工期の短縮・安定した品質・工事費の縮減などを目的として、昭和55年に日本で最初の組立マンホールが誕生しています。管理された工場で製造されているため、品質のバラツキが小さい・施工時間が短い・漏水が少ないなどの理由で下水道事業に多く使用されています。
主な特徴は下記のとおりです。
- 公的規格の製品である
平成元年6月1日付けで(社)日本下水道協会下水道用認定適用資器材II類に指定され、平成14年4月現在、17の組立マンホール工業会が認定されています。さらに、平成17年4月1日付けで(社)日本下水道協会下水道用認定適用資器材?類に登録され、JSWAS A-11(下水道鉄筋コンクリート製組立マンホール)となりました。当社は、昭和57年から自社開発の組立式マンホールを製造販売していましたが、その後全国コネクトホール工業会に加盟し、平成元年からコネクトホールの製造販売をしています。 - 工期の短縮ができる
高さ3m位の標準的なマンホールにおいて、底版・管取付壁・直壁・斜壁・調整リング・受け枠の組立作業が約40分、流入管・流出管の取付けを経て埋め戻し転圧まで約2時間半で終わりますので、速やかな交通の解放ができます。 - 余分な掘削が不要である
当社のコネクトホールは、外面に突起や連結部がありません。上下の製品の据え付け及び連結は内部で行いますので、余分な掘削は不要です。 - 漏水が少ない
当社のコネクトホールは、管理された工場の緻密なコンクリートで製造され、接合部は凹凸継手にブチル系ゴム材を張り付けウレタン系シール剤を充填し、上下の製品を3箇所をボルトで締め付け、さらに内面からモルタル目地を行いますので、漏水対策は完璧です。
鉄蓋と受け枠は何ですか
マンホールや汚水桝の入り口をふさぐためのもので、鉄蓋は、マンホールの中で唯一路面にでるため、市町村は独自のマーク又は模様を彫り込んでいます。受け枠の内径は、昭和50年4月7日付け労働省労働基準局長通達(下水道整備工事・電気通信施設建設工事等における労働災害の防止について)に準拠して、人間の出入りが行われる場合はφ600mm以上としています。直径634mmの円の中に市町村のアイデアとデザインが凝縮されているため、眺めているだけで気持ちが和みます。全国の模様を収集している方もいるようです。
調整部は何のためにあるのですか
マンホール深さの微調整を行うためと、将来路面の改修工事などを行う場合に、この部分から上を交換すれば簡単に行えることを目的に設けています。
鉄筋コンクリート製品(厚さ50、100、150mm)とモルタルで行う場合が多いですが、無収縮早強モルタルを使用することもあります。調整部の高さに制限はありませんが、あまり高くなると出入りが窮屈になりますので、その場合は下部の斜壁や直壁を高くしたほうが安全です。
斜壁は何のためにあるのですか
鉄蓋・受け枠とマンホール直壁部を連絡するために使用し、この部分で内径を変化させます。形状は、円錐台状に広がる両斜壁と片直円錐台状に広がる片直斜壁とがあり、近年は昇降の便利さから片直斜壁が多く使用されています。
場所打ち用と組立用 (コネクトホール) において、内径の変化は下記のようになります。
- 0号マンホール 〜 φ 600 → φ 750 (A0-N300、A0-N450、A0-N600)
- 1号マンホール 〜 φ 600 → φ 900 (場所打用 600A、600B、600C)
(組 立 用 A1-N300、A1-N450、A1-N600) - 2号マンホール 〜 φ 600 → φ1200 (場所打用 600D)
(組 立 用 A2-N300、A2-N450、A2-N600)
φ 900 → φ1200 (場所打用 900 )
(組 立 用 A2-N300N) - 3号マンホール 〜 φ 900 → φ1500 (組 立 用 A3-N300N)
直壁と管取付壁の違いは何ですか
従来、場所打ちで施工されていたおり、マンホールの本体にあたる部分で、流入管や流出管が取り付けられてました。組立マンホールが普及してからは、運搬や施工性の都合から流出管と流入管が取り付けられる部分を管取付壁、それから上の同一形状の開口部がない部分を直壁と呼ぶようになりました。ただし、直壁には副管用の流入穴が設けられることもあります。コネクトホール工業会では、円形は4号まで、角形は内のり3500mm×1500mmまで製品化されています。
副管付きマンホールとは何ですか
流入管と流出管の落差が600mm以上の場合には、マンホール外部の直近において流入管に鉛直方向のバイパス管を設け、流出管の管底より約20mm上げた位置でマンホールに接続します。
流入による側壁及び底部の摩耗を防ぐ役割を持っており、点検や清掃作業を容易にします。副管の大きさは、晴天時汚水量の汚水量を流下させることができる大きさが理想ですが、困難な場合はできるかぎり大きな径のものとします。
施工上の都合でマンホールの内部に設置 (内副管) することもあります。
足掛け金物とは何ですか
足掛け金物は、マンホール内において人が昇降するために取付けられたもので、安全性と耐久性が要求されます。
コネクトホールは、1号以下は幅300mm、2号以上は幅400mm、心材の直径φ22mm、ポリプロピレン樹脂被覆のものを使用しています。
平成8年のJIS A 5317 (下水道用マンホール側塊) の改正にともない、足掛け金物の項が削除されましたが、将来にわたって安全性と耐久性が望まれることは変わりません。
中間スラブとは何ですか
マンホールが深くなると、人間の体力及び心理面から昇降に恐怖心を覚えます。
そこで、3m〜5m間隔でφ600mmの穴を設けた中間スラブを設置し、一休みできる場所を確保するとともに、上から最下部が直接見え難くして恐怖心を和らげるようにします。
従って、足掛け金物は中間スラブの上下では反対方向の側壁に付くようになります。
なお、底部での維持管理作業のため、底部から中間スラブまで2m以上確保したほうがよい場合もあります。最近は、FRP製の後施工タイプが任意の高さに取り付けられる為、主流になりつつあります。
コネクトホールの組み合わせはどのようにしていますか
コネクトホールでは、管取付壁が7種類、直壁が8種類、斜壁が3種類、調整リングが3種類あり、同じ高さでも様々な組み合わせができます。
施工歩掛りは、高さが同じであれば組み合わせには関係ないようになっていますので、残るは製品単価・施工性・漏水対策が重要な要素になります。
以上の要素を検討した結果、管取付壁と直壁にできるだけ高さの高い製品を用い、深い位置での継ぎ目を少なくするように心がけています。
製品単価や施工性の面からも、この組み合わせが有利なことがわかりました。
コネクトホールはどのような使い分けをしますか
コネクトホールは、設置場所の状況に応じて適切な種類の製品を使用していただくため、部材の厚さと鉄筋量を変えてI種標準・I種特厚・II種標準・II種特厚の4種類に分けています。
主な特徴は、下記のとおりです。
- I種標準〜路面から底版上面までの深さが 5.00m以下の場所に設置します。
- I種特厚〜路面から底版上面までの深さが 5.00m以下の場所に設置し、矢板の引き抜きを考慮する場合の最下段に使用します。
- I種標準と比較すると、部材厚は1.2倍、主鉄筋量を約1.3倍増やしています。
- II種標準〜路面から底版上面までの深さが10.00m以下の場所に設置します。
- I種標準と比較すると、部材厚は変わりませんが、主鉄筋量は約1.7倍増やしています。なお、矢板の引き抜きを考慮する場所では、斜壁下部から特厚上部までの直壁にも使用します。
- II種特厚〜路面から底版上面までの深さが10.00m以下の場所に設置し、矢板の引き抜きを考慮する場合で、深さが5.00m〜10.00mの範囲に使用します。
- I種標準と比較すると、部材厚は約1.2倍、主鉄筋量を約1.3倍増やしています。
コネクトホールの鉄蓋中心と底版中心の偏心量はいくらですか
コネクトホールを設置するにあたり、鉄蓋中心と底版中心の偏心量は、掘削位置・流入管及び流出管の取付け・足掛け金物の方向を決める上で必要になります。 3号までの偏心量を下記に示します。
- 0号 (φ600 → φ 750) 〜 40mm
- 1号 (φ600 → φ 900) 〜 115mm
- 2号 (φ600 → φ1200) 〜 285mm 600鉄蓋 → 2号斜壁 → 2号
- 2号 (φ600 → φ900 → φ1200) 〜 265mm 600鉄蓋 → 1号 → 2号スラブ → 2号
- 2号 (φ900 → φ1200) 〜 125mm 900鉄蓋 → 2号特殊斜壁 → 2号
- 3号 (φ600 → φ900 → φ1500) 〜 415mm 600鉄蓋 → 1号 → 3号スラブ → 3号
- 3号 (φ600 → φ900 → φ1500) 〜 407mm 600鉄蓋 → 1号 → 3号特殊斜壁 → 3号
- 3号 (φ900 → φ1500) 〜 392mm 900鉄蓋 → 3号特殊斜壁 → 3号
コネクトホールの開口部はどのようにして決めていますか
コネクトホールの大きさと流入管や流出管の大きさは、(社)日本下水道協会「下水道施設計画・設計指針と解説」 に規定されるマンホールの形状別用途に準じて決めています。
組立マンホールは開口部の大きさや隣接する開口部と位置によっては、コンクリート部分が少なくなり荷重に対してひび割れが生じるおそれがあります。
そこで、別途構造計算を行って、マンホールの大きさ・設置深さ・開口部の大きさなどの条件をもとにして、必要なコンクリート部分の残りを決めています。
従って、開口部の大きさと位置関係はコネクトホールの強度に大きな影響を及ぼします。
コネクトホールの耐震対策は十分ですか
コネクトホールの耐震検討は、平成13年4月に発刊された(社)日本下水道協会「下水道施設耐震計算例」 に基づいて行います。
部材の大きさ・地盤の種別・表層の深さ・土の単位重量・土層の厚さ・部材の高さなどによって、断面力が変化し耐力も変わります。
主な結果を下記に示します。
- 地盤のN値
曲げモーメントやせん断力は、N値が2付近で最大になります。 - 表層の深さ
曲げモーメントやせん断力は、表層の深さが14m付近で最大になります。 - 土の単位重量
曲げモーメントやせん断力は、土の単位重量が18(kN/m³)・19(kN/m³)・20(kN/m³)と重くなるにつれて、大きくなります。 - 土層の厚さ
曲げモーメントやせん断力は、土層の厚さには影響を受けないようです。 - 部材の組み合わせ
曲げモーメントやせん断力は、同じ高さであれば、継ぎ目を増やして多くの部材を組み合わせたほうが小さくなります。
道路製品編
歩車道境界ブロックの種類と用途を教えて下さい
歩車道境界ブロックは、歩道と車道の境に設けるものですが、歩道と車道の構造によって下記に示す色々な種類が使われています。
- 片面歩車道境界ブロック
歩道が車道よりも高くなっている部分(以後マウンドアップと呼ぶ)に使用します。歩道側は 垂直で、車道側は少し勾配がついています。製品長は、600mmと1990mmとなっています。呼び名と高さは下記に示すと おりです。
- A 〜 高さ200mm
- B 〜 高さ250mm
- C 〜 高さ300mm
- 片面歩車道境界ブロック切下げ型
交差点や歩道の乗り入れ部において、歩道の高さを車道の高さまですり付ける必要がある場所に使用します。標準部から乗り入れ部までの間に、下記のような組み合わせの製品を用いて歩道の切下げを行います。なお、車道から歩道に向かって、左と右の製品に分かれます。
- A 〜 1本の長さが600mmの製品を1本用いて、200mm→100mmとなるように切下げるものと、1本の長さが1250mmの製品を1本用いて、200mm→100mmとなるように切下げるものがあります。
- B 〜 1本の長さが600mmの製品を3本用いて、250mm→200mm、200mm→150mm、150mm→100mmとなるように切下げます。
- C 〜 1本の長さが600mmの製品を4本用いて、300mm→250mm、250mm→200mm、200mm→150mm、150mm→100mmとなるように切下げます。
- 片面歩車道境界ブロック切下げ型 (バリアフリー対応)
交差点や歩道の乗り入れ部において、歩道の高さを車道の高さまですり付ける必要がある場所に使用します。標準部から乗り入れ部までの間に、下記のような組み合わせの製品を用いて歩道の切下げを行いますが、その勾配はバリアフリーに対応して5%になっています。この製品も、車道から歩道に向かって、左と右の製品に分かれます。
- A 〜 1本の長さが1000mmの製品を2本用いて、200mm→150mm、150mm→100mmとなるように切り下げます。
- B 〜 1本の長さが1000mmの製品を3本用いて、250mm→200mm、200mm→150mm、150mm→100mmとなるように切下げます。
- 片面歩車道境界ブロック乗り入れ型
車道から歩道へ乗り入れが必要になる場所が沢山ありますが、下記に示すように、身障者用に対応したものと、自動車に対応したものとに分かれます。又、直線部用と曲線部用があります。
- A 〜 身障者用は、車道側高さ70mm、歩道側高さ100mmのクサビ形をしており、長さは600mmです。自動車用は、歩道側・車道側とも高さ100mmの片直台形をしており、長さは600mmです。
- B 〜 身障者用は、車道側高さ70mm、歩道側高さ100mmのクサビ形をしており、長さは600mmです。自動車用は、歩道側・車道側とも高さ100mmの片直台形をしており、長さは600mmです。Aと似ていますが、幅が異なります。
- C 〜 身障者用は、車道側高さ120mm、歩道側高さ150mmのクサビ形をしており、長さは600mmです。自動車用は、歩道側・車道側とも高さ100mmの片直台形をしており、長さは600mmです
- 両面歩車道境界ブロック
歩道と車道が同じ高さの部分 (以後、フラットと呼ぶ)、又は、歩道が車道よりも少し高くなっている部分 (以後、セミフラットと呼ぶ) に使用します。断面は、歩道側と車道側が対称形になっています。製品長は、600mmと1990mmとなっています。呼び名と高さは下記に示すとおりです。
- A 〜 高さ200mm
- B 〜 高さ250mm
- C 〜 高さ300mm
- 両面歩車道境界ブロック切下げ型
交差点や歩道の乗り入れ部において、ブロックの高さを車道の高さまですり付ける必要がある場所に使用します。歩道の縦断勾配を気にする必要がありませんので、長さ600mmの製品を1本用いて行います。
- A 〜 1本の長さが600mmの製品を1本用いて、200mm→100mmとなるように切下げます。
- B 〜 1本の長さが600mmの製品を1本用いて、250mm→100mmとなるように切下げます。
- C 〜 1本の長さが600mmの製品を1本用いて、300mm→100mm (セミフラットの場合は150mm)となるように切下げます。
- フラットの場合 〜 両面歩車道境界ブロックの断面
- セミフラットの場合 〜 身障者用の断面
- 両面歩車道境界ブロック乗り入れ型
車道から歩道へ乗り入れが必要になる場所が沢山ありますが、両面歩車道境界ブロックは、自動車が乗り入れする場所に使用します。A・B・Cとも高さ100mmの両面型になっていますが、幅は異なります。 - 国土交通省両面歩車道境界ブロック乗り入れ部
国土交通省のバリアフリーに対応した、両面歩車道境界ブロックA型の乗り入れ部の全体構造は次のように分かれます。
- 横断歩道部 〜 標準型→共通切下げ型→横断歩道部用乗り入れ型
- 車両乗り入れ部 〜 標準型→共通切下げ型→車両乗り入れ部用切下げ型→車両乗り入れ部用乗り入れ型
- 共通切下げ型 〜 1本の長さが600mmの製品を1本用いて、200mm→70mmとなるように切下げます。
- 横断歩道部用乗り入れ型 〜 1本の長さが600mmで高さは70mmの両面型になっており、用心鉄筋を配置しています。
- 車両乗り入れ部用切下げ型 〜 1本の長さが600mmの製品を1本用いて、70mmの両面型 →歩道側70mm・車道側50mmの傾斜両面型で、用心鉄筋を配置しています。この製品は、車道から歩道に向かって、左と右に分かれます。
- 車両乗り入れ部用乗り入れ型 〜 1本の長さが600mmの製品で、歩道側70mm・車道側50mmの傾斜両面型で、用心鉄筋を配置しています。
鉄筋コンクリートL型の使い方を教えてください
呼びが350以下のL型は狭い道路の路面排水用側溝として使用しますが、呼びが500のL型は一般道路の路面排水用側溝として使用します。いずれも、エプロン部と縁石が一体化した構造と機能を備えています。使用場所は、通常は大型車両がのることはないが、一時待避などで低速の大型車両が載る場所に使用し、仮にひび割れが生じても路面排水側溝としての機能を保持できるような場所に使用します。主な特徴は、下記のとおりです。
- 呼びが350以下
製品長さは600mm、縁石部の大きさは、厚さ100mm、高さ100mm、エプロン部の横断勾配10%となっています。
乗り入れ製品は縁石部の高さが50mm、標準製品と乗り入れ製品を接続する切下げ製品は、長さ600mmの製品で縁石部の高さが100mmから50mmに傾斜しています。 - 呼びが500
製品長さは2000mm、縁石部の大きさは、歩車道境界ブロック A・B・C、エプロン部の幅は500mm、エプロン部の横断勾配は6%となっています。乗り入れ製品や切下げ製品の種類は、歩車道境界ブロックに準じています。
法先ブロックの使い方を教えてください
かつては畑や農道の端などにおいて、捨て石を積んで段の崩壊を防いだり、簡単な畦をつくり隣地との境界を示したりしていました。法先ブロックは石積みの労力を軽減し、用地境界を明確にできるなどの利点があるため、法面や段が形成されてからかなりの年月が経過し、土の移動が生じない場所に使用します。
従って、ごく微少な表土の流下は防ぐことができますが、裏面の盛り土に対する擁壁としての機能はありません。
集水桝編
集水桝にはどのような製品がありますか
L型側溝やU形側溝の中間部や合流位置には集水桝が設置されますが、その主な用途は次のとおりです。
- L型側溝やU形側溝の流量が許容量を超えないようにするため、所定の間隔で桝を設け、既設の水路や道路下に埋設されている雨水管渠に排水します。
- L型側溝やU形側溝を流れる水に含まれるごみ・土砂・石などを堆積させ、雨水管渠にこれらの異物が流れ込むのを防ぎます。
主な種類は、次のように分けられます。
- L型集水桝
鉄筋コンクリートL型側溝や場所打ちL型側溝の中間部に設ける桝で、L型側溝の流量が許容量を超えない範囲で設けられます。上部はグレーチング構造で横断方向及び縦断方向ともL型側溝と同じ勾配になるように設置し、下部には150mm以上の泥だめが設けられており、道路外の水路又は、道路下の雨水管渠へヒューム管や塩化ビニール管を用いて排水します。
当社の製品では、鉄筋コンクリートL型側溝300用の中間部に設置する「区画整理用L型集水桝」、昭和50年代の半ばに建設省中津維持出張所の方々が考案し、直轄道路の場所打ちL型側溝中間部に設置されている 「msZ敷き集水桝」、建設省制定 「土木構造物標準設計第1巻 (側こう類・暗きょ類)」 に示される場所打ちL型側溝の中間部に設置する 「 L型街渠桝 」、大分市の下水道部が場所打ちL型側溝300の中間部に設置「 L型集水桝 」が該当します。 - 合流桝
工場製品のU形側溝や場所打ちU形側溝の中間部に設ける桝で、U形側溝の流量が許容量を超えない範囲で設けられます。上部はグレーチング蓋・鉄筋コンクリート蓋・鉄板蓋などが多く、下部はL型集水桝と同じ構造になります。
当社の製品では 「ニューパワー側溝用集水桝 」が該当します。
上記以外にご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
Copyright© ツルサキヒューム宇佐事業所 All Rights Reserved.